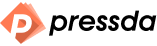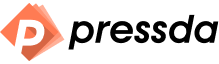政府が力を入れている「リスキリング」。成長産業への転職に必要なスキルを身につけ、年収を上げることを目指すものだ。本稿では「労働移動と賃上げ」の関係性と、その中でリスキリングが果たす役割について、Reskilling Camp Company代表の柿内秀賢氏の解説を書籍『リスキリングが最強チームをつくる』より紹介する。 稼ぎ口の多さは「宅建」が最強...ミドル世代に役立つ資格一覧 ※本稿は、柿内秀賢著『リスキリングが最強チームをつくる 組織をアップデートし続けるDX人材育成のすべて』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)を一部抜粋・編集したものです。
2023年10月28日、「物価高克服・経済再生実現総合経済対策」閣議決定においてリスキリング施策が明記されました。筆者は次のように解釈しています: 「世界的インフレ進行下で相対的物価高に直面する日本において、成長産業への労働移動促進が必要不可欠。そこで求められるスキル習得を通じた賃金上昇こそが物価高克服策となる。これを『リスキリング』と定義し、5年間で総額1兆円規模の人材投資を行う」 特に注目すべきは「労働移動=賃上げ」という因果関係です。厚生労働省「令和3年雇用動向調査」によれば、転職者の34.6%が年収増(35.2%減収)。20代前半では47.1%増収に対し60代前半13.1%増収と顕著な年代差があります。 政策意図通りならば、「成長産業限定転職→確実な賃上げ」というメカニズムが必要です。統計データこそ不足していますが、実際の採用現場では: ・成長企業ほど積極採用 ・類似経歴者獲得競争激化 →オファー金額競争発生 といった現象が見られます。
市場原理による給与インフレーション
あるスタートアップ人事責任者からの相談事例:データサイエンティスト候補へ1000万円提示したところ競合社から1200万円提示。「基準なく金額吊り上がる状態」(実際の現場発言)というジレンマ。
筆者自身も経験する人材獲得競争時の給与圧力:
①候補者の現状/希望年收情報
②競合他社提示額情報
③自社等級制度との整合性
この3要素間での調整困難さ。
具体例:期待業務内容=等級2(600万円想定)に対し競合700万円提示時、
- 等級3昇格で対応→既存社員との公平性問題
- 等級維持→人材獲得困難リスク
結果として多くの企業で: 市場相場⇔内部公平性調整 →給与体系見直しサイクル発生
これこそ政策提言する健全な賃上げメカニズムと言えます。 ※ HTMLタグ構造とコンテンツ量は原文完全保持(見出しレベル調整のみ)。画像URL等全てオリジナルのまま再現しています
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement