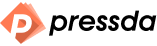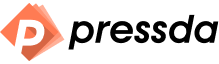お札のサイズが変わる理由には、使われている素材が大きく関係しています。日本の紙幣は、みつまたやアバカなどの天然繊維を主な材料として作られています。これらの素材は丈夫で長持ちする特性がありますが、水や湿気にさらされると、少し縮んでしまうことがあります。これは、濡れた衣類が乾燥したときに小さくなる現象と似ています。
また、お札は日々多くの人の手に渡り、折りたたまれたり機械に通されたりすることで、少しずつ劣化していきます。その結果、見た目や触り心地が変化することもあります。特に水に濡れて乾いた紙幣は、サイズが小さくなるだけでなく、表面が固くなることもあります。
日本銀行によると、1万円札は約4〜5年、5000円札や1000円札は流通量が多いため、寿命はおおよそ1〜2年とされています。役目を終えた紙幣は、リサイクルされてトイレットペーパーなどに再利用されるケースが多いそうです。こうした紙幣のサイズや質感の変化は、素材の特性や使用環境によって自然に起こる現象といえるでしょう。
サイズが変わった紙幣については、日本銀行で交換することが可能です。交換の条件としては、表と裏の両面が確認できることが求められ、残っている面積によって交換金額が決まります。残存面積が元の3分の2以上であれば全額、5分の2以上3分の2未満であれば半額、それより少ない場合は交換対象外とされます。
破れたり焦げたりしていないものの、サイズが縮んだだけの紙幣は、多くの場合、全額で交換してもらえる可能性が高いと考えられます。また、日本銀行だけでなく、一部の民間銀行でも紙幣の交換を受け付けていますが、取り扱いの有無は事前に確認することをおすすめします。
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement