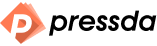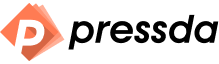「クソどうでもいい仕事(ブルシット・ジョブ)」はなぜエッセンシャル・ワークより高給なのか? その背景にある現代の労働観
ジョン・メイナード・ケインズが1930年に予測した未来、すなわちテクノロジーの進歩によって週15時間労働が可能になるというユートピアの実現。しかし現実には、私たちはむしろさらに長時間働かされ、そして無意味な仕事が増えていった。この現象の背後には、私たちの労働観に深く根ざした問題があるのかもしれません。
予測されたユートピアはなぜ実現しなかったのか?
ケインズの予測によれば、テクノロジーの発展は、労働時間を大幅に削減する方向に働くはずでした。しかし、実際にはその予測は外れ、技術はむしろ私たちをさらに働かせる手段として利用されるようになったのです。膨大な数の「クソどうでもいい仕事」が生み出され、結果として、多くの人々は心の中で無意味だと思いながら、日々その業務に費やす時間を持ち続けています。これは、現代の働き方が精神的・道徳的な面でも深刻な影響を与えている証拠です。
新たな仕事が増えた理由
20世紀を通じて、工業や農業の仕事は減少し、それに代わって専門職や管理職、事務職などが増えました。ケインズの予測通り、製造業はほぼ完全に自動化され、多くの新しい産業が台頭したものの、そのほとんどは「サービス業」ではなく、主に管理業務に関連した職種だったのです。これらの仕事は、私たちが本当に必要としている業務からは程遠いものです。
無意味な仕事の拡大
私はこれらの職業を「ブルシット・ジョブ(クソどうでもいい仕事)」と呼びます。何の役にも立たない、ただ働くために存在しているような仕事が、今や大多数を占めているのです。この現象は、資本主義社会の中ではあり得ないと考えられていました。しかし、現実には、そのような「無意味な仕事」が蔓延しています。
何が私たちを働かせるのか?
自由な時間を手に入れることが可能だったはずの時代に、支配階級はそれを恐れ、労働時間を延長する方向に社会を導いてきました。1960年代には、一度は労働時間削減が目指されましたが、それに対する強い反発が起こり、結局、現代のように長時間働く社会が続いているのです。これは「働くことが道徳である」とする社会的価値観が深く根付いているため、安易に変えることができなかったからです。
無意味な仕事に苦しむ人々
「クソどうでもいい仕事」に従事している多くの人々が、その無意味さに気づき、苦しんでいます。例えば、ニューヨークの大企業で顧問弁護士として働く友人は、自分の仕事が無意味であると痛感しており、世の中に何の貢献もしていないことを自覚しています。このような自覚は、今や多くの人々が持っているものです。
仕事の価値と報酬の逆転現象
さらに問題なのは、社会的に貢献のある仕事ほど低い報酬を受ける傾向が強まっていることです。例えば、公共交通機関の労働者がストライキを起こすと、彼らの仕事が本当に必要だという証拠にもかかわらず、一部のメディアはその反感を煽り立て、働く人々の不満を矛先を変えてしまいます。こうした現象こそ、現代社会が抱える最も大きなパラドックスであり、私たちが直面している問題です。
現代の労働社会において、私たちは本当に必要な仕事に従事しているのでしょうか?「ブルシット・ジョブ」が蔓延する背景には、深刻な社会的、道徳的、政治的な要因が絡んでいます。無意味な仕事の増加と、それに伴う報酬の逆転現象について、さらに掘り下げて考えることが求められています。
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement