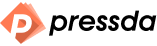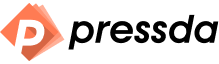視覚障害の人を助ける盲導犬は、認知度が高い。その一方で、世間にあまり認知されていないのは聴覚障害の人を支える「聴導犬」だ。聴導犬は、インターフォンが鳴った時や外出先で危険を感じた時などに必要な音をユーザーに知らせる。だが現在、聴導犬ユーザーは日本全国で50名ほどと少なく、盲導犬ユーザーと大きな開きがある。その背景には行政の金銭的支援が手薄なことや当事者が感じる聴導犬への葛藤など、様々な理由がある。
聴導犬になれる犬は年間1頭いるかいないか
「公益社団法人 日本聴導犬推進協会」は聴導犬の育成や普及、広報活動を行う。事務局長の水越みゆきさんは、自分が育てた犬たちが働いているうちは辞めないと決意し、28年にわたって聴導犬の育成や普及に携わってきた。
聴導犬の候補犬は動物愛護センターなどに収容されている生後2~4ヵ月の子犬から、性格などを加味して選出される。候補犬は、年間2~3頭ほど。実際、聴導犬になれるのは年間で1頭いるかいないかくらいだという。
「育成は早くて2年、長くて4年ほどかかります。仕事をしながら訓練を受ける希望者が多く、手話や言語アプリなどを使って聴導犬との関わり方を本当に理解できているかを確認しながら慎重に進めていくので時間がかかるんです」
聴導犬とユーザーは、互いを支え合う関係性でなければならない。聴導犬が、音を知らせてくれるペットや単なるセラピー犬にならないよう、ユーザーは経済的・精神的に自立し、犬が出したサインを読み取る力を養う必要があると水越さんは語る。
「互いが同じ方向を向いて支え合い、進んでいくからこそ聴導犬との関係は成り立つ。私たちは関係性が上手くいかない時に犬の気持ちを代弁して関わり方をアドバイスします」
金銭的負担や人手不足に悩む
盲導犬は全国で790頭ほどいると言われているが、聴導犬はわずか50頭。厚労省が公表した「令和4年 生活のしづらさなどに関する調査(全国在宅障害児・者等実態調査)」によれば、令和4年の身体障害者手帳を持つ視覚障害者の人数は27万3000人、聴覚障害者(言語障害も含む)の人数は37万9000人であった。本来なら、盲導犬と同じくらいの聴導犬がいてもおかしくはないのだ。
にもかかわらず、聴導犬の普及が進まない背景には金銭的な事情も関係している。基本的に聴導犬や盲導犬などの身体障害者補助犬の育成費などは寄付で賄われているが、聴導犬は認知度が低く寄付が集まりにくい。
「聴導犬1頭の育成には、300万~400万円ほどかかります。補助犬を1頭誕生させると行政から団体へ給付金が給付されますが、それは必ずもらえるわけではありませんし、ユーザーの住む県によって給付額も異なります」
例えば、東京都の場合は給付金を支払う補助犬の頭数が決まっており、既定の頭数を上回るほど補助犬の申請があった場合は、全額の補助犬に給付金が行きわたらない。宮城県では決められた予算を、その年に誕生した補助犬の頭数で割り、給付金を支払う仕組みだという。
金銭的に厳しいため、現在、公益社団法人 日本聴導犬推進協会では水越さんを含む2名のスタッフで聴導犬の育成や事務作業に取り組み、2名の非常勤スタッフが犬たちのお世話の補助を担っている。人手不足ゆえ、水越さんは勤務時間外も聴導犬の世話や育成に励む。
「給付金は期待しないようにしています。この現状は聴導犬や聴覚障害者に対する理解が進まないと変わらない。耳が聞こえないって体験することが難しい分、大変さが伝わりにくいと感じます」
“聞こえない人たちだけの世界”を作らせないために
一方で、聴導犬の普及には聴覚障害の人に聴導犬の役割を正しく伝えることも大切だと水越さんは語る。音を知らせてくれるのは便利だが、その先にある“必要性”が当事者に理解されにくいのが現状であるからだ。
また、聴覚障害の人は見た目で障害者であることが分からないため注目されることはないが、聴導犬という存在が一緒にいることで“目立つこと”に繋がる…と思い、聴導犬との暮らしを躊躇してしまうことも少なくないという。
「だからこそ、聴導犬が当たり前に存在する社会を目指しています。そうなれば、ユーザーは周囲の視線が気にならない。聴導犬は何かあった時に助けてくれる存在だという認知を広げていきたい」
公益社団法人 日本聴導犬推進協会は、聴導犬とトレーナーを育成できる施設を今夏に建設予定。ホームページでは、寄付を受け付けている。
聞こえる息子が反抗期に入って
では、実際に聴導犬と暮しているユーザーはどのような想いを抱いているのだろうか。生まれつき聴覚障害を持つ安藤美紀さんは2010年3月に1頭目の聴導犬レオン(MIX)くんを迎え、現在は2頭目の聴導犬アーミちゃん(ラブラドールレトリーバー)と暮らしている。
聴導犬を迎えようと思ったきっかけは、健常者の息子さんが反抗期に入ったことだった。来客時の音などを知らせてもらうことが難しくなり、常に神経を使わなければならない日常に精神的・肉体的疲労を感じたのだ。
「息子の帰宅が遅くなり、出かけることも増えた中で息子に甘えていたことに気づきました。息子には息子の人生があるので、おんぶに抱っこではいけないと悟り、聴導犬と一緒になり、家族の負担を減らそうと考えたんです」
安藤さんは2004年3月にオーストラリアで聴導犬訓練協会の見学をし、初めて聴導犬の存在を知った。帰国後、日本にも11頭の聴導犬がいることを知り、迎え入れたいと公益社団法人 日本聴導犬推進協会に相談。
「様々な協会に問い合わせを行う中で、犬のことを優先に考えているここなら安心だろうと感じ、面談を受けました」
レオンくんを迎えたのは、相談から2年後。いざ聴導犬を迎えてみると、誰かに気を使わなくても聞こえない音を知らせてもらえることに感動した。
「漫画を読んだり、テレビを見ていたりしても知らせてもらえるので心の余裕もできました」
レオンくんという心強い存在は、安藤さんの心を明るくもした。聞こえないことは悪いことではない。自然とそう思えるようになり、日常が楽しめるようになったのだ。
「レオンは、夏の終わりを告げる虫の音も教えてくれた。遠い昔、ペットだった犬のマミーが夏の音を教えてくれたことを思い出しました。夏の音だけでなく、秋の音もあるんだね、とベランダで幸せな気持ちを味わいました」
聴導犬ユーザーが感じた「社会の壁」
だが、一方で外出時には聴導犬の知名度が低いことから同伴拒否をされることも多く、歯がゆい思いをした。聴導犬は聴覚障害を持つ人にとって、いわば身体の一部だ。街中で出会っても触ったり、声をかけたりすることは控える必要があるが、その認識も社会に広まっているとは言いがたい。
「ケープに聴導犬と書いてありますが、2頭目の聴導犬アーミはラブラドールレトリーバーであるため盲導犬のイメージが強く、視覚障害者に間違われることも多いです」
また、聴導犬ユーザーは「共に支え合うパートナー」として聴導犬と向き合っているが、周囲からは「聴導犬に介護してもらっている」というイメージを持たれやすい。そうした認識のズレも、当事者と周囲の間に溝を生む理由のひとつとなっているのではないかと安藤さんは指摘する。
なお、アーミちゃんと暮らす中で安藤さんが痛感したのは、聴導犬と一緒に働くことの難しさだった。安藤さんは20年ぶりに企業で働くことを決意したのだが、思い描いていた未来は掴むことができなかったという。
「聴導犬を連れての電車通勤は、肉体的・精神的にキツいものでした。聴導犬を守れる自信もないと感じたため、会社に相談して週に一度だけ在宅ワークをさせてもらうことで落ち着きました」
聴導犬と一緒に働くことを優先すると出社が難しくなり、金銭的な不安を解消したいと願えば、聴導犬という心強いパートナーに頼らずに働くことを覚悟するしかない…。それは安藤さんが直面した、聴導犬ユーザーのリアルだ。
そうした聴導犬ユーザーの現状を変えるためにも、聴導犬の認知度が高まっていくことは重要である。本当の意味でインクルーシブな社会にしていくためにも、より多くの人に聴導犬とユーザーの現状が届いてほしい。
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement