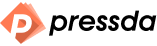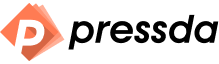20代で京セラを創業、50代で第二電電企画(現KDDI)を設立して通信自由化へ挑戦し、80歳を目前に日本航空の再生に挑んだ稲盛和夫氏。いくつもの企業を劇的に成長・変革し続けてきたイメージのある稲盛氏だが、京セラで長らく稲盛氏のスタッフを務めた鹿児島大学稲盛アカデミー客員教授の粕谷昌志氏は、「大変革」を必要としないことこそが稲盛経営の真髄だという。本連載では粕谷氏が、京セラの転機となる数々のエピソードとともに稲盛流の「経営」と「変革」について解説する。 第5回は、急速な市場拡大が見込まれる半導体産業に着目、実力重視の米国に活路を見出し、半導体部品を中核事業に育て上げた稲盛氏の挑戦の日々を振り返る。
■ 京セラの中堅企業化と事業構造転換 1967年1月16日の第1回経営方針発表を通じて、創業8年目にして中堅企業への道を歩み始めた京セラ。稲盛和夫は幹部社員の意識変革を促すとともに、社内体制を整備することに努めた。驚くべきは、その後わずか数年で将来にわたる中核事業をつくりあげ、中堅企業はおろか大企業への道を確かなものとしたことである。 ファインセラミック業界での後発メーカーであった京セラは当初、競合他社が断った困難な製品を受注することで市場開拓を行っていた。しかし試作中心で少量生産が続く状況から脱却するため、稲盛が着目したのが半導体産業だった。
■ シリコンバレーとの運命的な出会い 1969年にはフェアチャイルド社から画期的な多層ICパッケージ開発を受注。「サーバントたれ」という理念のもと24時間対応体制で信頼を得た結果、「技術者の独立後も発注が続く」という稀有なビジネス関係性を作り上げた。
■ 史上最大8億円受注との苦闘 AMIからの電卓用パッケージ100万個受注獲得後も量産技術確立まで2年間歩留まりゼロ状態が継続。鹿児島川内工場では夜行列車で通う稲盛自ら現場指揮を取り、「世界制覇」というビジョン掲げながら赤字累積との死闘が繰り広げられた。
■ 「最初で最後」の方針転換 1971年に全設備投資額7億円(当時)をつぎ込み量産ライン構築。「泥縄式投資原則」唯一例外となったこの決断により世界トップシェア獲得へ至る道筋を作り上げると同時に、「ケチ作戦」(徹底コスト削減)による財務健全性維持という二律背反マネジメントを見事両立させた。
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement