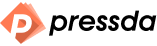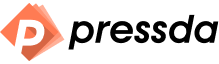個人の創造性や技術、才能に基づくクリエイティブ分野を、富と雇用を創出する可能性がある「産業」として捉える「クリエイティブ・エコノミー」。今、その可能性に世界が注目している。 そもそも、クリエイティブ産業の価値を測る最初の取り組みを行ったのは、1997年イギリスの文化・メディア・スポーツ省が出版した『クリエイティブ産業 – マッピング文書1998』。広告、建築、芸術品および骨董品市場、工芸品、デザイン、デザイナーファッション、映画、インタラクティブレジャーソフトウェア、音楽、舞台芸術、出版、ソフトウェア、テレビとラジオという13の分野をクリエイティブ産業として定義した。 一部で「クリエイティブは、体系的な分析などが可能な生物科学や工学などの分野からも生まれる」という反論も生み出しながらもあえて社会的・文化的領域に限定しその分野の経済的な推進力を図ろうという調査で2001年の追加調査では実際にこれらのクリエィテヴ産業か多くの雇用を生み出しているとして注目された。
遺跡保全×現代アート:ウズベキスタンの新たな試み
WCCEでは昨年オープンしたばかりの中亜Expo会場で80ヶ国から200人の参加者が集結。中でも注目されたのがACDF財団主導の「未来志向型遺跡保全プロジェクト」だ。歴史的建造物を単なる博物館ではなく現代アーティスト創作拠点とする画期的試みは投資誘致策(民間投資分免税)と連動し国民的支持も得ている。
シルクロード新時代:伝統技術と国際協力
失われたレンガ技法復活のために招聘されたのは20年以上カーブルの遺跡修復に関わったAfghan職人チーム。「過去保存だけではない未来創造装置」として設計されるArtist in Residenceプログラムでは選考委員長Cyrille Zammit(仏人キュレーター)らが国際性と地域共生バランス重視(最低1室は地元作家枠)の方針を示した。2024年9月プハラビェンナーレでは修復過程自体か展示コンテンツとなる予定だ。
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement